子どもの頃に少しだけ触れたタロットカード。
占いが大好きな私は、その不思議な絵柄やめくるときの緊張感やときめきに惹かれていました。
大人になった今、改めて「ちゃんと学んでみたい」と思い、もう一度カードと向き合いはじめました。
…とはいえ、まだまだ初心者。
わからないことだらけで、いろんな本やサイトを読みながら、手探りの日々です。
この記事では、そんな私が「これは知っておいてよかった!」と感じたタロットの基本や、実際に使ってみて気づいたことなどをまとめています。
もしよければ、あなたも一緒にこのカードの世界をのぞいてみませんか?
※本記事は筆者の個人的な体験に基づいて書かれています。
占いの効果を保証するものではありませんが、タロットに興味を持つ方のヒントになれば幸いです。
タロットができること、その使い方とは?
幼い頃に、雑誌の付録でタロットカードがついてきました。
「タロットって当たるの?」
「そもそも、どんなふうに使うのだろう?」
出たカードの意味を考えたりすることが楽しくて、一枚ずつめぐるたびにワクワクしたことを覚えています。
現在の私は、未来をズバリ当てるためのもの、というよりも、
「いまの自分の気持ちを整理する」
「心の奥の声に気づく」
そんな使い方のできるツールだと、捉えています。
たとえば、迷っているとき。
心の奥ではもう答えが出ているのに、見ないふりをしているとき。
カードは、そっと気づかせてくれる存在だと感じています。
タロットカードの歴史
タロットの起源は14世紀ごろのヨーロッパ。
もともとはトランプのような遊び道具として使われていたそうです。
その後、19世紀〜20世紀にかけて神秘思想や占星術と結びつき、さまざまな流派や解釈が生まれ、
占いの道具として発展しました。
現在は「ウェイト版(ライダー版)」が世界的に主流で、アーティストによる美しいオリジナルデッキもたくさん登場しています。
アートとして集める人も多いのです。
タロットデッキの種類と選び方
タロットには大きく分けて2つのスタイルがあります。
■ マルセイユ版
- 歴史的に最も古いデッキのひとつ。
- 解釈にはある程度の訓練や想像力が必要。
- 小アルカナはトランプのような記号的な絵柄で構成。
■ ウェイト版(ライダー版とも)
- 現在最もポピュラーなスタイル。
- 小アルカナにも絵柄が描かれており、意味がイメージしやすい。
- 初心者にはこちらが断然おすすめ。
私自身は、ウェイト版を選びました。
ウェイト版は、自分が見慣れていることと、タロットの本でもこちらの絵柄で説明がなされていることが多いからです。
また、カードを見たときの直感や「好きかも」という気持ちが選ぶ決め手になると思います。
直感は、タロットと仲良くなる第一歩かもしれません。
私は一般的な真ん中のサイズにしましたが、少し手に余るかも?
扱いに慣れるまでは小さ目サイズがいいかもしれません。
▶ライダーウェイト版を買った体験談はこちらから

タロットカードの構成と意味のヒント
タロットカードは全部で78枚。
その内訳は、大アルカナ22枚と、小アルカナ56枚に分かれています
■ 大アルカナ(22枚)
- 「愚者」「魔術師」「女帝」「運命の輪」「塔」「世界」など。
- 人生の大きなテーマや変化、気づきを表す。
子供の頃は、占い雑誌の付録の大アルカナだけで占っていました。
意味がドラマチックでわかりやすいため、入り口としてピッタリですね。
でも最近になって、日常の細かなことやちょっとしたニュアンスを知りたいときには、小アルカナが必要だと感じています。
■ 小アルカナ(56枚)
小アルカナは、日常の出来事や心の動きを映すカードたちです。
スートは次の4つ:
| スート | エレメント | キーワード |
|---|---|---|
| ワンド | 火 | 情熱・行動 |
| カップ | 水 | 感情・愛情 |
| ソード | 風 | 思考・決断 |
| ペンタクル | 地 | お金・物質 |
この4つの分類が、星座と同じように「火・水・風・地」の4つのエレメントに分けられていて、理解しやすかったです。
さらに、小アルカナは次のように分かれます:
- 数札(スートカード):エースから10まで :日常の出来事、小さな変化
- 宮廷カード(コートカード):ページ、ナイト、クイーン、キング →:人間関係や自分の中の多面性
特にコートカードはスートごとに個性が違うので、見ているだけでも楽しいです。
例えば、同じクイーンでも全然様子が違います。
例:
- ソードのクイーン → 知的で冷静(キリッとしてる)
- カップのクイーン → 優しげで慈悲深い(天使っぽい)
- ワンドのクイーン → 堂々と自信あり(ヒマワリ&アゴ上げ)
- ペンタクルのクイーン → 控えめで堅実(下を見てコインを抱えてる)
今は自分で占いながら、出てきたカードから少しずつ覚えていこうとしています。
私がつまずいたポイントと、乗り越え方
🔸 意味を丸暗記しようとするとツライ
→ 50代の脳には無理があります(笑)
まずは「カードを見たときの印象」を大事にしています。(例えばレイアウトや色は?)
🔸 逆位置(さかさま)の意味が難しい
→ 無理に読まず、最初は正位置だけ。慣れたら少しずつ。
(意味は反対だったり弱まったり、質問に応じて)
🔸 リーディングに自信がもてない
→ でも大丈夫。1日1枚ひいてノートに書くだけでも、ちゃんと進歩してます!
タロットは、心のカウンセリングカード
最近私は、タロットカードを占い道具というよりも
「自分の気持ちに気づくためのカウンセリングカード」だと思うようになりました。
当たる・当たらない、を超えて、
自分でも気づかなかった視点、再確認できるきっかけ
をくれるのが、タロットカードの魅力です。
焦らず、楽しみながら
カードと対話し仲良くなる時間を、これからも大切にしていきたいと思います。
関連記事はこちら
▶オラクルカードも挑戦中です
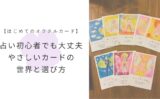


コメント